-

会員管理システム

会員管理システム
-
会員管理システムでは、次の機能がご利用いただけます。
・会員情報の照会・更新
・会費納付状況
・会誌発送状況
・パスワード変更
・オンライン名簿・会員検索システム
・オンラインクレジット決済システム
-
会員管理システムでは、次の機能がご利用いただけます。
-

学会を知る
-

イベントに参加する

イベントに参加する
-

活動にふれる

活動にふれる
-
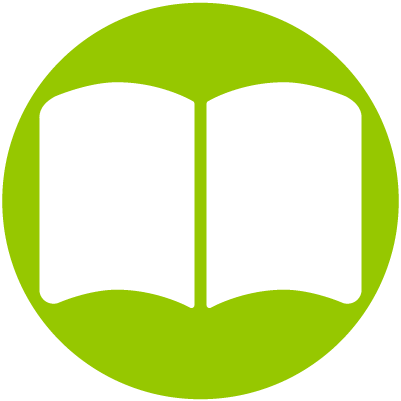
出版物を見る
大学教育に関わる知の交流と実践による革新を進め、
学術に根ざした成果を広く世界に発信して、社会に貢献する教養ある人間の育成に寄与します。
TOPICS
NEWS
-
- 2024-04-17お知らせ
- 【公募情報】札幌医科大学医療人育成センター入試・高大連携部門(2024年5月29日必着)
会員一般
-
- 2024-04-12大会・集会
- 第46回 大会申込みを開始しました。
会員一般学生
-
- 2024-04-11大会・集会
- 大学教育学会 第46回大会のご案内を更新しました。
会員一般学生
-
- 2024-04-01お知らせ
- 【公募情報】大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンターキャリア教育部(2024年5月10日17時必着)
会員一般
-
- 2024-04-01お知らせ
- 【公募情報】大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター教学質保証部(2024年5月10日17時必着)
会員一般
OUTLINE
「一般教育・教養教育の理念・目標」や「各大学の自由で多様な発展」が
大学自体の研究・改革の成果として実現するよう、
わが国大学教育百年の視野における展望を切り開いていくことを願い、
これからもパイオニア的役割を果たして行きます。
1979年12月「一般教育学会」として発足した大学教育に関するパイオニア的学会です。
発足以来一貫して大学教育の大衆化に伴う「大学教育研究」の開拓を志向し、かつ広範な大学教員が参加する「大学教員としての自己研究」活動(FD型研究活動)に主眼をおいて活動をしています。
知識基盤社会が進展し、大学教育の果たす役割の重要性が再認識されるなかで、大学教育の改革に関して、いわゆる現代化を推し進めるとともに、本来的な人間形成機能の再生をめざしています。






